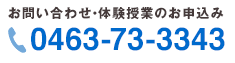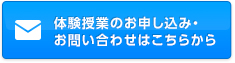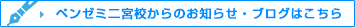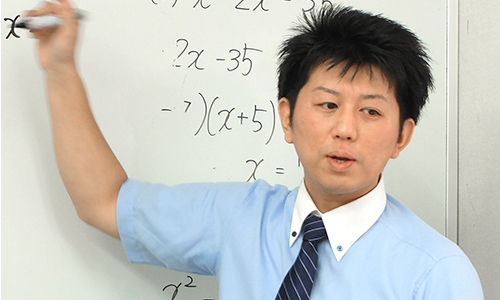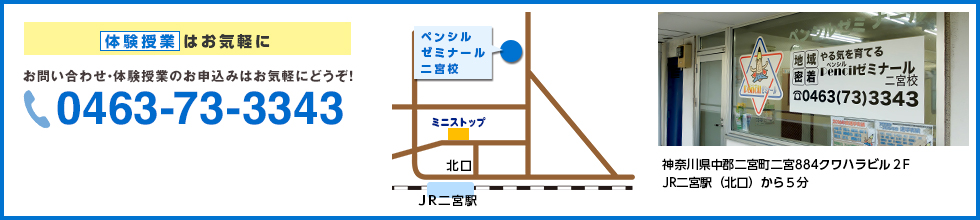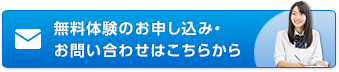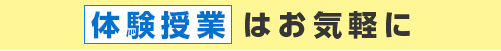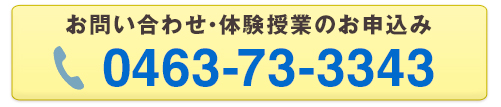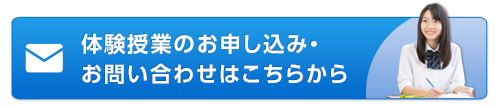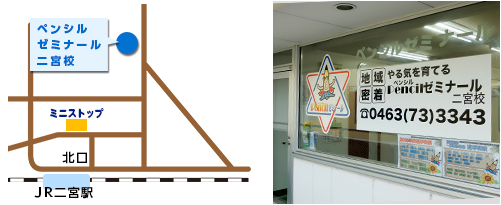1学期期末テストを振り返って
2021年07月12日(月)
例年よりも早く6月21・22・23日に1学期期末テストがあった。今回は月曜からはじまる定期テストで土日の使い方が非常に難しかったこと、更に9日前には体育祭もあり、切り替えがどれだけ早くできるかがポイントとなった。
全員のテスト結果が揃ったので少しその点について書こうと思う。
1学期期末テスト
致し方ないことかもしれないが中学校間・学年でかなりの平均点の差が生じている。先生によっても難易度が違うのは致し方ないが、やはり定期テストが地区で統一されて欲しいと願うばかり。今年度から二宮中学の「マイステップ(点数分布)」が非常に見やすく改善された。点数層への階級がしっかり分かり生徒たちも自分がどの位置にいるのか把握できるようになった。それに対して二宮西中学は、平均点のみとなった。例年では中央値まで記載があったが…。私自身は中央値の方を気にしていたので少し残念である。
中1生
二宮中
案の定といっても良いが、英語が中学はじめての定期テストとしては難しいテストだった。英作もかなり出題されていた。ペンゼミとしては、良い問題と感じているがかなり鍛えていないと9割は取れない。数学はかなりバランスの良いテストだったように思う。あのテストで平均58.9点、更に点数分布から、授業についてこれてない生徒も多い学年ということが分かる。
二宮西中
英語は、「はじめての定期テスト」というテストだった。「最初から英語を嫌わないで」というメッセージかな!?数学も同様、基礎問題が非常に多く、ミスをどれだけしないかが勝負。というテスト。同じ地区でも今回のテストは二宮中が難しかったように感じるし平均点でもそのように出ている。
| 二宮中学 | 英語 | 数学 |
|---|---|---|
| 平均点 | 60.2 | 58.9 |
| ペンゼミA | 84.3 | 78.7 |
| 二宮西中学 | 英語 | 数学 |
|---|---|---|
| 平均点 | 71.2 | 61.3 |
| ペンゼミA | 83.3 | 77.3 |
中学生になりはじめてのテスト。生徒たちに「何を感じたか」を問うと「部活も休みになってビックリした」「ワークを早くやらなくちゃいけないと思った」など、しっかり学んでくれたと思う。この反省(PDCA)を1年間くり返し、2年ではしっかりと結果につなげてもらいたい。中には「先生が言っていた9割にいかなくて悔しいです」という生徒もいた。その気持ちを周りにも伝染させたい。
中2生
二宮中
前評判通りかもしれないが、数学では発展問題が出題され平均53.8点。この学年は、中1時から平均50点前後(一番低い時は43.1点)という学年。問題をしっかり選定して自分のできる問題を確実に解くことが大事。英数に比べて国理社は非常に平均点が高く平均65点付近。9割以上取れないと成績5は見えてこない。
二宮西中
英語の平均が53.4点と非常に低いが、それ以外の科目は60点から65点。テストで確認したい力をしっかり見極めるテストとしては非常に良いテストだと感じている。前回テストでかなり難しい科目もあったので、調整がされているように感じた。基礎学力をしっかり身に付ければ点数アップもしやすく結果につながるテストだったのでかなり点数アップした生徒がいた。
| 二宮中学 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均点 | 56.8 | 53.8 | 68.7 | 64.0 | 64.9 |
| ペンゼミ | 64.8 | 70.3 | 69.7 | 76.1 | 75.1 |
| ペンゼミA | 83.2 | 85.0 | 83.6 | 89.4 | 90.4 |
| 二宮西中学 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均点 | 53.4 | 62.6 | 64.0 | 61.4 | 60.7 |
| ペンゼミ | 67.8 | 74.5 | 73.7 | 76.0 | 66.3 |
※二宮西Aクラスは2名のため平均点を記載しておりません
前回点数より35点(5科目合計)以上アップした生徒9名。9割取った生徒がいたり、転塾してきた生徒も50点アップしたり、Aクラス二宮平均432点などかなり伸びてきた学年。以前、ブログにも書いたが今回もPクラスでは「石井塾」をやってしっかり成果も残してきた。自身にもつながってくれたのではないかと思う。
中2生 ついに始動〔石井塾〕
中3生
二宮中
前回の数学が70.3点と以上に簡単なテストだったが、今回は55.5点。理系に弱い学年であの難易度でかなり苦しかった。点数分布からも80点前半から成績5がつきそうだ。社会の平均が72.8点と非常に高くミスをどれだけしないかというテスト。教科間の平均のばらつきが非常に大きい。この学年の二宮中生は比較的、文系が強い。顕著に結果として出た。
二宮西中
テスト後、生徒たちが口を揃えて「英語・国語が難しかった」と言っていた通り英語・社会の平均点が低い。英語は英作が非常に配点が高く、中1・2までの内容の理解が非常に大事だった。国語は入試の傾向に沿った問題だが、現在の入試国語は点数源になるのに対し、難しめ。まだ生徒たちも対応できていないということかな。理科は平均点層がボリュームゾーンではないのだと思う。できる子・できない子に二分しているように感じる。
| 二宮中学 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均点 | 57.8 | 55.5 | 71.0 | 62.3 | 72.8 |
| ペンゼミ | 71.5 | 63.2 | 77.5 | 74.8 | 84.1 |
| ペンゼミA | 72.0 | 70.3 | 83.8 | 79.7 | 91.7 |
| 二宮西中学 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均点 | 54.3 | 65.7 | 51.8 | 57.6 | 59.4 |
| ペンゼミ | 67.3 | 86.5 | 65.9 | 79.7 | 69.3 |
| ペンゼミA | 83.0 | 92.0 | 76.2 | 88.2 | 74.0 |
最後の学年のビックイベント体育祭からの切替ができたかどうかが大きなポイントとなった。大きく点数を伸ばした生徒は、体育祭練習でもヘトヘトになりながらも優先順位をしっかり考えて行動できていた子だったように思う。例年と比べるとAクラス・Pクラスとの差が小さいので、今後クラスの入れ替えも出てくるように思う
ペンゼミ日記